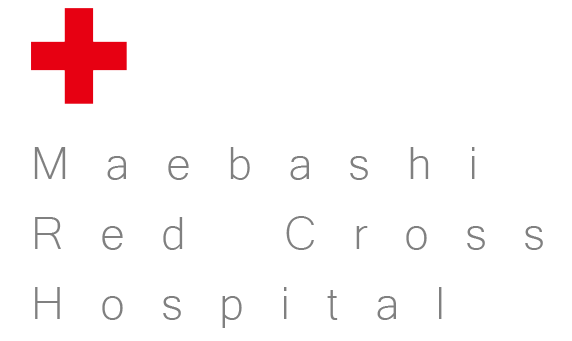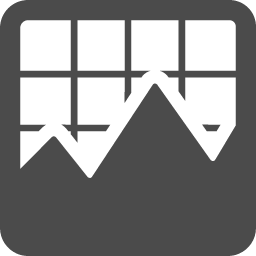 臨床工学技術課
医療提供側、医療受療側、双方から信頼されるよう努めます。
臨床工学技術課
医療提供側、医療受療側、双方から信頼されるよう努めます。
臨床工学技術課は、血液浄化療法センター・心臓カテーテル室・手術室・高気圧酸素室・ME機器管理室・ICU・ 病棟など、院内各所で医工学に係わる業務を担当する専門集団です。治療の現場では、医師の指示のもとに医療機器の操作設定を行い、使用後や保 管中の医療器機を定期的に点検・管理しています。また、当院は三次救急を担う病院であり、24時間緊急症例に対応するため臨床工学技士も夜勤 体制をとっています。
理念
医療提供側、医療受療側、双方から信頼される臨床工学技術課を目指します。
基本方針
1.医療安全を第一に、医学的根拠(エビデンス)に基づいた技術を提供します。
2.災害・救急医療に常時対応できる体制を構築します。
3.スタッフ同士の協力と話し合いを通じ、良好な職場環境を作ります。
4.病院健全経営のために臨床工学技術を提供します。
業務内容
血液浄化業務
主に血液透析とアフェレシス関連の業務です。治療原理は異なりますが、「血液浄化」の名前の通り、共に血液 をきれいにする治療です。
血液透析
腎臓機能の低下により体内に蓄積した尿毒素や過剰な水分などを人工腎臓により取り除く治療です。当院においては、血液浄化療法センター にて実施するほかに、ICUなどへ臨床工学技士が出向いて実施する(出張透析)場合もあります。
血液浄化療法センターの紹介
計36床の透析ベッドを備えています。月・水・金は午前と午後の2クール、火・木・土は午前の1クールの血液透析治療を行って います。また、アフェレシスも数多く実施しています。

アフェレシス
血液浄化療法の一種です。体液(主に血液)から病気の原因となる物質を分離・除去する治療です。アフェレシスには様々な種類があり、幅 広いアフェレシスに対応している点が当院の特徴と言えます。以下に、代表的なアフェレシスを挙げます。
血漿交換療法
血液から血漿成分を分離除去し、除去した血漿成分と同量の置換液(新鮮凍結血漿製やアルブミン製剤)を補充する治療法です。重症筋無力 症や血栓性血小板減少性紫斑病、ANCA関連血管炎など幅広い病態に適応されます。
吸着療法(血漿吸着療法・直接血液還流療法)
血液に含まれる病気の原因となる物質を、血液中から吸着して除去する治療法です。血液を直接吸着材へ接触させる方法では、難治性潰瘍性 大腸炎に適応される白血球除去療法(G-CAP)や敗血症に対するエンドトキシン吸着などがあります。また、血液成分と血漿成分を分離 し、血漿成分のみを吸着材へ接触させる方法には、家族性高コレステロール血症や難治性ネフローゼ症候群に対するLDL吸着療法や肝性昏睡 に対するビリルビン吸着療法があります。
腹水濾過濃縮療法(CART)
肝不全や癌性腹膜炎などによって腹水が貯まってしまう難治性腹水に対する治療です。腹水に含まれる癌細胞や細菌などを除去し、アルブミ ンや免疫成分を回収・濃縮して患者さんの体内へ戻すことで、栄養状態や免疫力の改善をはかりながら自覚症状を改善させます。
その他のアフェレシス
上記以外にも様々な種類があります。当院で実際に実施されている、実施実績のあるアフェレシスは次の通りです。単純血漿交換、選択的血 漿交換、LDL吸着、免疫吸着、ビリルビン吸着、エンドトキシン吸着、活性炭吸着、G-CAP、リクセル、腹水濾過濃縮療法(CART) です。
出張透 析・出張アフェレシス
手術後の方や救命センターに入院中で状態の安定しない方は、ICUなどで出張透析治療を実施しています。様々な病態に合わせて、血液透 析、持続的腎代替療法(CRRT)、各種アフェレシスなど幅広く対応しています。
医療機器管理業務
医療機器の安全使用を確保するために、定期的に機器の点検を行っています。また、昼夜問わず機器使用中に発生するトラブルへの対応もし ており、医療機器に関わる全般を担っています。当院の医療機器安全管理者の役は臨床工学技士が就いています。
機器管理 業務
実際の業務としては、機器の使用後の清掃および動作点検を行い、異常がないことを確認して次の使用に備えることがメイン業務で す。また、一部の機器は定期点検も臨床工学技士が実施しています。

機器の計画的 運用
機器管理の作業は、機器管理専用のソフトウェアに入力・記録しています。これにより、各機器の使用(故障)履歴の管理、また、稼働率な ども容易に算出することができます。これら情報を用いて、病院と機器の更新時期について話し合うなど、医療機器(病院資産)の長期的な運 用にも携わっています。医療機器管理業務は、一見地味な業務ではありますが、病院を運営する上で必須の業務です。
他職種に向け た勉強会の実施
臨床工学技士が講師となり、定期的に他職種へ向けた勉強会を実施しています。例えば、新人看護師へ向けた輸液ポンプ・シリンジポンプの 勉強会は毎年臨床工学技士が講師を務めています。他分野においても言えることですが、臨床工学技士は講師の立場になる機会が多い職種で す。
手術室関連業務
手術室では以下の業務にあたっています。
体外循環関連 業務
心臓の手術(開心術)をする場合、一時的に心臓を止めなければなりません。その際、手術中の生命を維持する役割を担うのが人工 心肺装置です。臨床工学技士はこの人工心肺装置を中心に、心筋を保護する心筋保護装置などの監視・操作を行なっています。加え て、手術後に必要に応じて使用される補助循環装置(IABP・ECMOなど)の対応もしています。

ロボット支援 手術(Da Vinci)関連業務
ロボット支援手術(Da Vinci)では手術が安全に施行できるよう、各装置の準備と設定などを行っています。

ハイブ リッド手術室関連業務
主に、経カテーテル大動脈弁留置術(TAVI)に関連した業務です。TAVIとは、開胸せず、心臓が動いている状態で、カテーテルを 使って大動脈弁の代わりとなる人工弁を運搬・留置する治療法です。臨床工学技士はクリンプとポリグラフ操作・心内圧測定などの外回り業務 を行っています。また、大動脈ステントグラフト内挿術(EVAR・TEVAR)の際には、IVUS操作も行っています。
その他の 手術室業務
手術室では術式に応じてさまざまな医療機器が使用されます。臨床工学技士は心臓血管外科手術や整形外科手術で使用される自己血回収装置 の操作や機器の日常点検や定期点検を行っています。
心臓血管内科業務
心・血管カテーテル関連業務と不整脈治療関連業務に携わっています。緊急対応を要する症例が多いため24時間対応できるよう、夜勤・待 機態勢を整えています。
心・血管 カテーテル関連業務
心臓カテーテル検査とは、カテーテルを上下肢の血管に経皮的に挿入し、その中を進めて目的の血管に到達させ、透視装置と造影剤を用いて 狭窄血管を診断します。血管の狭窄に対して、バルーンによる拡張やステントの留置などを実施します。
ポリグラフ(心臓カテーテルモニタリングシステム)の操作
ポリグラフを使用して心電図の記録をしています。他にも「心拍出量の測定」「心内圧の測定・解析」「心内シャント率の測定」などを行っ ています。
血管内イメージング装置・冠内圧測定システム(Physiology) の操作・データ管理
血管内超音波検査法(IVUS)と光干渉断層法(OCT)で得られた画像や心筋血流予備量比(FFR)などの情報を医師へ提供します。
デバルキング装置の管理
デバルキング(Debulking)とは石灰化病変や動脈硬化病変を削りとる治療です。ロータブレータ(RAS)・ダイヤモンドバック (OAS)・方向性冠動脈粥腫切除(DCA)があり、専用装置が必要です。この装置を管理・セッティングしてPCI(経皮的冠動脈形成 術)の治療補助にあたっています。
補助循環装置 の操作・管理
大動脈内バルーンパンピング法(IABP)、体外式膜型人工肺(V-A ECMO)の導入時の機器操作を主に行っています。また、補助循環導入後に病室へ移動した後も、定期的に使用中点検にて作動状態を確認しています。
不整脈治療関 連業務
不整脈に対して行う治療で、植え込み型心臓電気デバイス(CIEDs)関連業務や電気生理学的検査(EPS)・カテーテルアブレーショ ンなどがあります。
植え込み型心臓電気デバイス(CIEDs)関連業務
CIEDsとは心原性不整脈に対する植え込み機器の総称です。植込み手術から退院後の経過観察まで関わっており、医師の指示の下に設定 変更を行います。定期外来で作動状態や不整脈の履歴チェックを医師の指示のもと行います。また、植え込み患者が電気メスを使用する手術の 際や、MRI撮影を実施する際にも、安全確保のために立ち会います。
植え込み型心臓電気デバイス(CIEDs)の種類
心臓ペースメーカ(PM)、植込み型除細動器(ICD)、両心室ペーシング機能付き植込み型除細動器(CRT-D)、植込み型両心室 ペースメーカ(CRT-P)、植込み型心電図モニター(ICM)などが挙げられます。
一次的(体外式)ペースメーカの操作
緊急症例における徐脈やペースメーカ植え込みまでの繋ぎに使用されるカテーテルデバイスです。医師の指示の下に設定変更を行います。
電気生理学的検査(EPS)・カテーテルアブレーション・スティムレー タ・3Dマッピングシスシテムの操作
EPSは心臓内にカテーテルを挿入し、不整脈の原因となっている電気経路を見つけるための検査です。カテーテルアブレーション はその不整脈を発生させている原因の組織を焼灼する治療です。

集中治療業務
ICUにおける人工呼吸器、持続緩徐式血液濾過透析やアフェレシスなどの血液浄化装置、V-A ECMO・V-V ECMO やIABPなどの補助循環装置の準備や操作、管理を行っています。
使用中の医療 機器の管理
人工呼吸器や体外循環装置(CRRTやECMOなど)の稼働中は臨床工学技士がラウンドし、安全運転していることを確認しています。他 にも、一酸化窒素(NO)吸入装置や血行動態モニタなども管理しています。これらのトラブルシューティングにも24時間対応しています。
他職種カン ファレンスへの参加
ICUでは医師、看護師、薬剤師、リハビリテーションスタッフ、栄養士など様々な職種が従事しています。患者様にとって最適な治療を決 定するために毎日全ての職種が集まりカンファレンスを行い、治療方針を決定しています。臨床工学技士も積極的に参加しています。
ECMOプロ ジェクト
ECMO(Extracorporeal membrane oxygenation)とは患者さんの血液をポンプで体外に引き出し人工肺で充分に酸素を与えて再び体内に戻すという体外式膜型人工肺です。 当院では日本呼吸療法医学会ECMOプロジェクトに参加しています。 医師・看護師と連携して院内マニュアルの作成やトレーニングを行うことで、安全なECMO管理が行えるよう努めています。

高気圧酸素療法
この治療は大気圧より高い気圧環境の中で、高濃度酸素を吸入することにより血液中の酸素量を増加させ、酸素不足の組織や損傷を 受けている組織を回復させるものです。当院では主に一酸化炭素中毒、突発性難聴、骨髄炎や放射線障害の治療に使用されます。
高気圧酸素治療装置
当院では写真のような装置を採用しています。これは高気圧酸素治療装置の中で「第1種装置」と呼ばれる1人用の治療装置です。装置の外で臨床工学技士が付き添い、装置操作や 心電図モニタを用いて治療にあたっています。

各学会認定資格取得状況
当課は認定資格の取得に励んでいます。また、学会や講習会への参加に対して、病院より支援がある点が特徴です。当課の取得認定資格は以 下の通りです。
血液浄化関連
- 透析技術認定士
- 血液浄化関連専門臨床工学技士
- 日本アフェレシス学会認定技士
機器管理関連
- 臨床ME専門認定士(第1種ME技術者)
循環器関連
- 体外循環技術認定士
- 心血管インターベンション技師
- 植込み型心臓デバイス認定士
- 心・血管カテーテル関連専門臨床工学技士
- 不整脈治療関連専門臨床工学技士
- CDR認定(CDR :Cardiac Device Representative)
集中治療関連
- 認定集中治療関連臨床工学技士
人工呼吸器関 連
- 3学会合同呼吸療法認定士
- 呼吸治療関連専門臨床工学技士
その他
- 臨床実習指導者講習会修了者