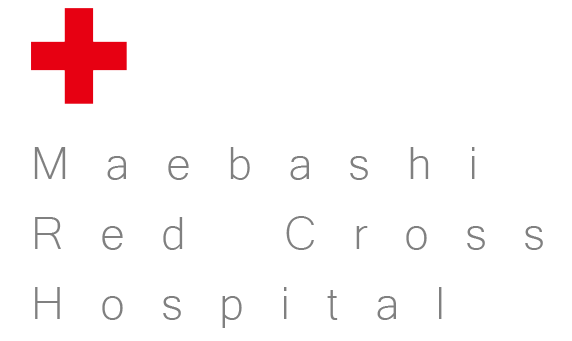臨床研究・治験について
臨床研究とは
病気の原因や解明、診断や予防、治療方法や治療薬、治療機器等を改善、開発し、患者さんの生活の質の向上などのために行う研究 を臨床研究といいます。臨床研究の実施の手続、認定臨床研究審査委員会による審査意見業務の適切な実施のための措置、臨床研究に 関する資金等の提供に関する情報の公表の制度等を定める「臨床研究法」が平成29年4月に公布されています。
治験とは
臨床研究のためには、開発の最終段階で多くの患者様に使用していただき、製薬会社の研究者や医師が病気の原因について詳しく研 究し、「くすりのもと」になりそうな物質を探します。 選別された「くすりのもと」は、動物を対象にその物質の有効性と安全性を詳しく調べます。病気に対して効果が期待でき、大きな副 作用がないことが確認されたとき「くすりの候補」となります。 ここで「くすりの候補」は実際に人を対象に試験を行ないます。これを「治験」と呼びます。
臨床研究に関する情報公開について
臨床研究は、対象となる患者さんの診療情報を利用することから、あらかじめ本人の同意を得るのが原則です。本人から「事前の同 意」を得ることを「オプトイン」(opt-in)とも言います。これに対して、あらかじめ本人に対して個人データを第三者提供す ることについて通知または認識し得る状態にしておき、本人がこれに反対をしないかぎり同意したものとみなし、研究の実施について 情報を公開、さらに拒否の機会を保障することがことを認めることを、「オプトアウト」(opt-out)といいます。これらの診 療情報からは、お名前やご住所など、個人が特定されるような情報は削除し、また研究の成果は学会や雑誌等で発表されますが、その 際にも個人が特定される情報は公表しません。また、研究不参加を申し出られた場合でも、患者さんの診療内容に何ら不利益を受ける ことはありません。
以上を踏まえ、当院でオプトアウトを行っている臨床研究を以下に掲示します。
治験の流れ
「治験」は通常、第Ⅰ相試験、第Ⅱ相試験、第Ⅲ相試験の3つのステップで段階的に進められます。これらの試験結果がまとめら れ、国(厚生労働省)の厳しい審査をパスしたものが「薬」として発売されることとなります。
 第Ⅰ相試験
第Ⅰ相試験
少数の健康な成人を対象とし、「くすりの候補」の安全性を確認する試験です。はじめて人に投与されるため、医 療体制の整った専門の施設で行なわれます。 前橋赤十字病院では、第Ⅰ相試験は実施していません。
 第Ⅱ相試験
第Ⅱ相試験
少数の患者さんを対象とし、効果的で安全な用法や用量を調べる試験です。
 第Ⅲ相試験
第Ⅲ相試験
多数の患者さんを対象とし、他の標準的な「薬」や薬効のない物質(プラセボ)と比較して、有効性や安全性を確 認する最後の試験です。
治験審査委員会
治験は「くすりの候補」を人に使用するため、参加される患者さんの人権や安全が厳格に守られなくて はなりません。このため国により厳しいルールが定められています。これを「医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令」(略称 GCP)といいます。病院には医師をはじめとした医療従事者、医療を専門としない事務などの職員さらに病院外の有識者を集い治験 審査委員会が設置され、治験の計画や内容、患者さんの人権が守られ安全性に問題がないかなどが月1回審議されています。
治験審査委員会の構成
| 医師 | 臨床検査技師 | 薬剤師 | 事務 | 院外委員 |
|---|---|---|---|---|
| 4名 | 1名 | 1名 | 2名 | 1名 |